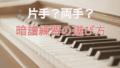こんにちは、いのうえちづよです。
以前、別の記事で、

学生の頃バッハのインベンションは片手ずつ練習、暗譜までしてから両手で初めて合わせるという練習方法を取っていました
ということを書いたのですが、この練習には注意点があります。
今日はこのことについて書きます。
片手ずつの暗譜練習には注意点がある
バッハのような対位法的な曲では有効
バッハのインベンションは、どちらかというと同じようなメロディが両手で繰り返されるという作りになっています。
なので、それぞれ覚えるのは覚えやすいという利点があります。
でもすべての曲に向いているわけではない
ところが、例えば左手の演奏が全音符が延々と続く音でできている場合や二分音符でできたりしている場合、それを覚えてから弾くというのはかなり無理があると考えています。

なんかつまんないかも
単純な音符の繰り返しの場合は、意外と覚えにくかったりするのではないでしょうか。
こういう場合は、むしろ両手で暗譜するように最初から両手で譜読みをしていくほうが音楽として捉えやすかったりします。

いきなり練習してもいいのね
音楽としての“流れ”を意識しよう
子どもの生徒さんに楽譜を作る時、ひとつのメロディを両手で演奏するように編曲する時がありますが、こういう場合も気をつけないといけない事は、どんな音楽なのか意識する必要があるということです。
単調な伴奏やリズム音型は暗譜が逆に難しい
例えば、バッハのインベンションなどは、右手も左手もメロディが流れているので、それぞれを覚えればいいんだけど、両手で1つのメロディを演奏するような場合は、片手だけの暗譜は難しいんですね。
左手を演奏する場合、四分音符だけの単純な羅列だったりするとなかなかに音楽として覚えるのは難しいですもんね。
両手で弾いたほうが全体の音楽が見える場合
最初に申し上げた通り、例えばバッハのインヴェンションなどの場合は、左右別々に暗譜をして両手を合わせた方がメロディラインが音楽的になるのでおすすめなのです。

ふにゃあ
どんなときに“両手での暗譜”がおすすめ?
右手にメロディが集中している場合
先ほども書いたように、右手にメロディ、左手は伴奏系の場合の方が両手で覚えやすいです。

童謡の曲とか・・?
簡単な構成で、耳と感覚で覚えやすい曲
コードなどで覚える場合は、右手にコードの中の構成音から2つ、左手は根音などの場合は、耳で聴きながら覚えるという方法がうまくいくと思います。

コードを両手で演奏したりするば場合ですね。
片手練習だけにこだわらないで
練習の「いつものクセ」を見直してみよう
自分の練習では、必ず片手から、左手から、両手からで練習ではなくて、曲の感じを見て練習方法を考えてみるのも1つの手です。

こだわっちゃうんだよね・・・・・。
曲の構成・目的に応じて、柔軟に方法を選ぼう
曲の構成や目的を考えながら、臨機応変、柔軟に練習方法を選んでみてね。

練習方法や譜読みのちょっとした工夫は、メルマガでもご紹介しています。今回のような「曲のタイプ別アドバイス」も、ぜひチェックしてみてくださいね。
まとめ|音楽は“ひとつ”として感じながら練習しよう
少し簡単なメロディの場合、そして右手にメロディが固まっている場合、常に両手で一緒の演奏で暗譜もした方がいいです。
譜読みの段階でちょっと自信がついてきたなっていう時には、最初から両手奏で挑戦してみてくださいね。
今日もお読みくださってありがとうございました。