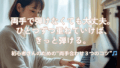こんにちは、いのうえちづよです。
ピアノを始めてしばらくすると、こんな悩みを抱くことがありますよね。

あたし、譜読みが意外とできる方で、譜読みが終わると、すぐ弾けちゃうから……飽きちゃうんですよね〜。
実は、譜読みができた=曲が仕上がった、ではないんです。
今日は、“曲を仕上げる”ために欠かせない、もう一歩進んだ練習のコツをご紹介しますね。
譜読みが終わっても「仕上がり」とは限らない
譜読みや部分練習、通し練習などの「基本の練習」はもちろん大切です。
でも、そこまでできるようになったら、次のステップに進んでみませんか?
次のステップは……
です。それは“味わいながら練習する”ような感覚です。
仕上げ練習って、どんなことをするの?
「曲を素敵に弾きたいな」「このフレーズをもっと表情豊かにしたい」
そんな気持ちが出てきたら、仕上げ練習のチャンスです。
以下の3つの視点を持つことで、演奏が一気に深まります。
1. 曲の背景を知る
2. 作曲家の思いに触れる
3. 音を“出す前”から意識する
① 曲の背景を知る

たとえば、バッハの時代はパイプオルガンが主流でした。演奏もこの楽器でした。
パイプオルガンは、音がずっと鳴り続ける特徴があります。
そのため、スタッカートが書かれていなくても、音を少し切るように弾くことがあるんです。
② 作曲家の思いに触れる
「マズルカ」や「ワルツ」など、タイトルに含まれる言葉からヒントを得ましょう。
ブルグミュラーの曲のように、物語性があるタイトルのときは、情景を思い浮かべながら弾くとぐっと味わいが増します。
③ 音を“出す前”から意識する
鍵盤を押した瞬間、もうその音は戻せません。
だからこそ、音を出す前から、すべてを整えておく必要があるのです。
- 手の構え
- 体のバランス
- ペダルの足の位置
- 指づかい
すべてが一音の響きに関わってきます。
たった1小節に向き合う価値
レッスンでは、生徒さんに
とお伝えすることがあります。
そのくらい、1〜2音にじっくり向き合うことには価値があります。
たとえば“ファ”の音。
そのたった1音を、何度も何度も打鍵して、自分の「理想の音」に近づけていきます。
すると自然に、耳が育ち、指の感覚が研ぎ澄まされてきます。
プロのピアニストはどう練習している?

プロのピアニストの人たちって、毎回そんなふうに細かく考えて弾いてるの?

ううん、そこまで意識してないかも。というのも、プロはすでに「自分の音」を体に覚えさせているから、自然とできちゃうんだと思う。
でも、そんなピアニストたちも、毎日練習しています。
それは、自分の音をさらに磨くためなんです。
「飽きる」はステップアップのチャンス
もし、練習がつまらない、飽きてしまうと感じたら、それはチャンス!
もしかしたら、“目標”が浅いところにあるだけかもしれません。
「なんとなく弾けた」ではなく、
そんなふうに感じるようになったら、練習がもっと面白くなりますよ。
レッスンで得られる気づきとは
自分ひとりではなかなか気づけない“音の向き合い方”。
レッスンでは、先生がその手助けをしてくれます。
「この音、もっと柔らかく」
「ここのフレーズ、深呼吸するように」
そういったアドバイスがあるからこそ、演奏の世界が広がっていきます。
難しく感じずに、自分の音として練習してみてくださいね。
まとめ:1音1音と向き合うことで、自分の音が育っていく
- 譜読みができたら、次は「表現」へ。
- 1音に向き合う練習は、表現力をぐんと高めます。
- 自分の“理想の音”を見つけていくことが、ピアノの楽しみ。
噛めば噛むほど、味わい深くなるこの練習。
焦らず、少しずつ取り組んでいきましょう。
あなたのピアノが、もっとあなたらしく響きますように。
素敵な演奏を、聴かせてくださいね。
自分の音にじっくり向き合うヒントは、無料メルマガでもお届けしています。