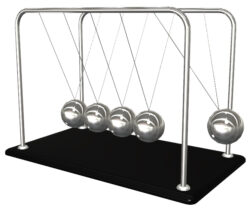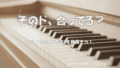こんにちは、いのうえちづよです。
寒くなると、手がいつまでも暖まらずにガチガチなので、弾き間違いと音はずしの多い事、多い事。これって、やっぱり、鍵盤の幅を指が覚えていて、寒いと指が鍵盤のいつもの幅に広がらないという事でしょうかね。
スポーツのようにピアノも準備体操をしたほうがいいですね。ストレッチなどもしてから演奏に臨みましょう。手が冷たい時は、あまり無理はしないでね。
「手首を制する者は演奏を制す」—その理由とは
私は、地元にあった音楽短大を卒業しています。
今は、4年大学に吸収されて、その学校はありません。
学校生活は、夏休みもなくて、とにかく忙しい日々でした。
ピアノの科目と別に、教員取得のための過程を受講していたからです。
その夏期集中講座の中に、指揮法というのがありまして、指揮の勉強をしたのですが、最初はみんな指揮なんて出来ませんから、結構、面白い指揮をしていました。
もちろん私も(^^;)
指揮から学ぶ手首の柔軟性とリズム感
演奏側に回って見ていると、見にくい指揮、見やすい指揮というのがあるんです。
見にくい指揮はですね、動きに緩急が無いと言うか、一定の速さをしている指揮です。
教員時代に、よく子どもたちがこういう指揮をしていました。
手から手首、腕まで一直線にして、指揮をしていました。
例えば、振り子のように、ちゃんと折り返し地点があって、そして点から点までの動きに勢いがある事が良い指揮ですが、これがない指揮に合わせると音がバラバラになるんです。
演奏者の方が、それぞれ折り返し地点を決めちゃっているからですね。
さらに、正しい棒の振り方というのは、小刻みに降るにしても、大きく降るにしても、手首の動きというのが大切なんだと学びました。
なめらかな曲線を描くのは、手首が柔軟じゃないと、動かせません。
かと言って、手首だけで降るとかくかくしてしまって、やっぱりあまり良くないんです。
ちゃんとその曲の様子に合わせて、手首を使う必要があったんですね。
バイオリンやトロンボーンにも共通する手首の使い方
この事を踏まえると、弦の動きもそうなんですよね。
主科は、ピアノですが、副科でも楽器を専攻しないといけなくて、副科では、バイオリンを専攻していました。
希望は、クラリネットだったのですが、希望者が多くて、はずれちゃっただけです。とても残念な思い出です。
バイオリンなどの弦楽器の弓を動かす時は、手首が滑らかに動く方は、演奏が流れるようで、とても音楽的でした。
プロの方の演奏を見ていても、手首の返しが、綺麗ですものね。
ピアノ演奏でも響きが変わる「柔らかい手首」
ピアノの演奏も一緒で、手首ががちがちだとピアノの音もたどたどしく聴こえるんです。
音も硬いです。
これって、楽器全般の演奏に通ずるものなのかなと思います。
子どもの教室の生徒さんで、金管バンドに所属している生徒さんがいます。
彼女は、トロンボーンを習っています。
トロンボーンって、長い管のような部分を前後に動かしつつ、音程を決めていくんです。
その際に、やっぱり、手首の動きが重要なんですよ。
手首を制する者は、演奏も制す
なんだなあと、思いました。
レッスンでも伝えている“お化けの手”の意味
レッスンでは、お化けお化け~の手ですよとお伝えしていますが、お化けの手も手首が柔らかくないと意味がありません。
柔らかい手首になるように、おいでおいで〜の練習は効果的です。

おいで〜、おいで〜・・。ひっひっひ。
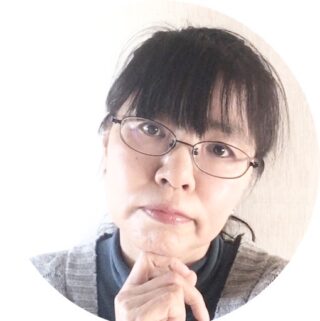
まとめ:手首の動きで変わる、あなたの音楽表現
今日は、指揮法を学んだ時の、手首の柔らかさの必要性から、楽器全般での手首の必要性について書いてみました。
今日もお読みいただきありがとうございました。
手首の感覚や柔らかさは、文章で読むだけではなかなか伝わりにくいもの。
レッスン現場で実際にお伝えしているコツや補足のヒントを、メルマガでも少しずつご紹介しています。