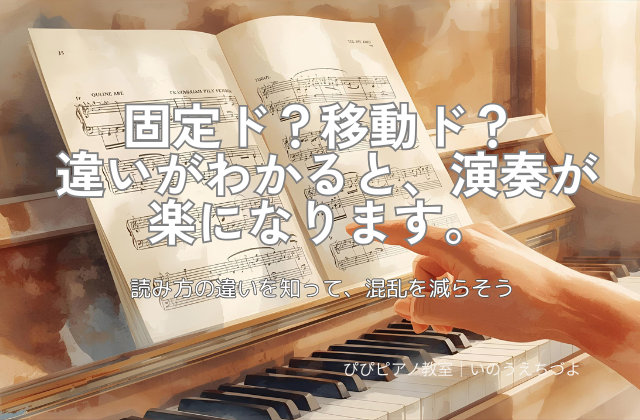こんにちは。いのうえちづよです。
生徒さんからよくこんな質問をいただきます。

耳コピーをするときに、聴こえてくる“ドレミ”と、楽譜に書かれている音が違うんです。私、音感がまだまだなのかしら?
これは実は「音感がない」というよりも、音の読みが2種類あるから起こることなんです。
ドレミには2種類ある?読み方の基本
音を読むときには、大きく分けて
- 固定ド読み
- 移動ド読み
という2つの方法があります。
固定ド読み:いつでも「ド」は「ド」
これはとてもシンプルです。
「ドはいつでもド。ファはいつでもファ。」
つまり、どんな曲でも音の名前は変わりません。
例えると、「地図に書かれた地名」みたいなもの。
東京はどこに行っても“東京”と呼ぶのと同じです。
移動ド読み:調(キー)によって「ド」が変わる
こちらはちょっと変わっています。
「曲の調(キー)によって、“ド”の場所が変わる」読み方なんです。
例えば、ハ長調の“ド”と、ヘ長調の“ド”は別の音になります。
その代わり、どの調でも必ず「ドレミファソラシド」と歌えるようになります。
たとえ話でわかる!固定ド vs 移動ド
固定ドは「地名」、移動ドは「出発駅からの順番」
これは「駅名ではなく、出発駅から数えて“1駅目、2駅目…”と呼ぶ」ようなイメージ。
場所は変わっても、順番で考えればわかりやすい、ということですね。
それぞれの使いどころを知ろう
どちらも正しい読み方で、使い方が違うだけです。
楽譜の読みやすさなら固定ド
子供の頃から習う「音楽」の教科では、この固定ド読みで読むので、ほとんどの人には読みやすいと思います。
固定ドは、楽譜を読むときや普段の練習に便利ですね。
移調や耳コピなら移動ドが活躍
移動ドは、曲を別の調に移して(移調して)弾くときに便利。
趣味ピアノではどちらを使う?
大人の独学ピアノなら「固定ド」でOK
音楽大学を目指すような方は両方を学びますが、趣味でピアノを楽しむ方なら、固定ドだけで十分です。
でも移動ド的な感覚も自然と育つかも
移調や転調などをする場合には、移動ド読みも役に立つので、使っているうちに自然に読み方を学べるかもしれないですね。
🎁「独学ピアノでも、音感を育てたい!」という方へ
メルマガでは、大人のピアノ初心者さん向けに、音感の育て方や読み方のコツをやさしくお届けしています。
まとめ|“ドレミの違い”は、感覚が育ってきた証かも?
「ドレミが違って聴こえる…」と感じたときは、音感がないのではなく、移動ド的に聴こえているのかもしれません。
これはむしろ、和音の響きや調性を感じられるようになってきた証拠です。
難しく考えず、「あ、音楽の感じ方が一歩進んだんだな」と思ってみてくださいね。