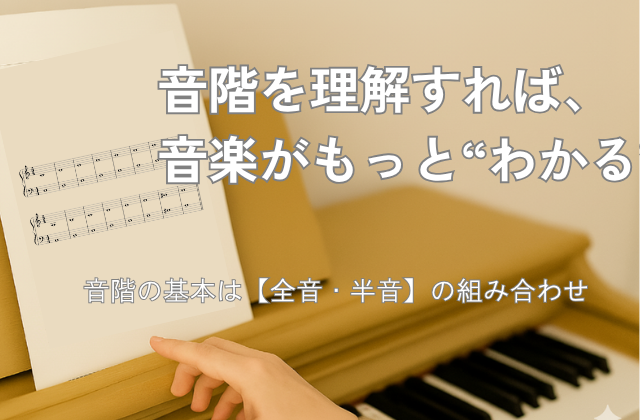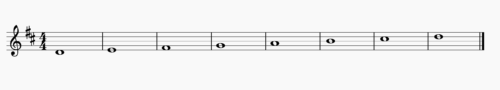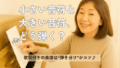こんにちは、いのうえちづよです。

音楽の基礎として、音階を覚えると良いと聞きました。でも数が多くてなかなか覚える事ができません。覚えるための良い方法はありませんか?
音階には、仕組みがあって、仕組みを覚えると音を覚えなくても演奏する事が出来ます。
今日は、この事について書いてみますね。
音楽の専門内容になりますが、普通に演奏する時にも役立つ【大切な基礎の部分です。】
音階は“音のまとまり”。まずは仕組みを理解しよう
音楽を作っているものに、音階と言うのがあります。
音のまとまりのことで、これは、音楽を演奏するのに必要なものです。
曲には使う音が決まっている=材料が違えば味も変わる
音楽も作りたい「調」によって、使う音が変わるんです。

調・・?

そう、例えば、ハ長調やニ長調、ト長調やヘ長調などのことだね

使う音が変わる
料理で例えると
クッキーを作ろうと思ったら、小麦粉、バター、卵が必要で、
プリンを作ろうと思ったら、卵、砂糖、エッセンスなどが必要。
チーズケーキを作ろうと思ったら、普段の材料にクリームチーズを加えますよね。
このそれぞれの材料の部分が音階となるんです。
それぞれの調に合わせて使う音が決まってきます。
なんとなくの音を使って作られているわけではないんですね。

そだね
音階は24個。覚えるより「理解する」ほうが近道!
さらに、音階は、24個あります。
この音階をすぐに演奏出来るといいのですが、なかなか覚えるのが大変です。

覚えるのかあ・・。
ハ長調で作ろうと思ったら、調号無しの音階になるし⬇️

調号無し
ニ長調で作ろうと思ったら、シャープが2つ付いた音階になります⬇️

ニ長調は、シャープが2つ
それを1つ1つ覚えていたら、本当に大変です。
そこで、仕組みで覚える方法をお伝えしますね。

よっしゃ、仕組み!
音階の基本は【全音・半音】の組み合わせ
仕組みを覚えるために、一つだけ理解して欲しい事があります。
それは、全音と半音という音の幅です。
仕組みを覚えるためには、
まず、全音と半音という音の幅を理解しましょう。
全音・半音とは
【全音】
全音とは、音と音の間に鍵盤が1つある音の幅の事。
【半音】
半音とは、音と音の間に鍵盤が挟まっていない音の幅の事。↓
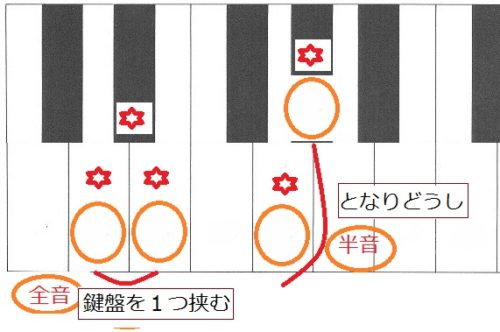
では、この全音・半音を使って仕組みを解説してみますね。
長調の音階は【ぜ・ぜ・は・ぜ・ぜ・ぜ・は】でできている!
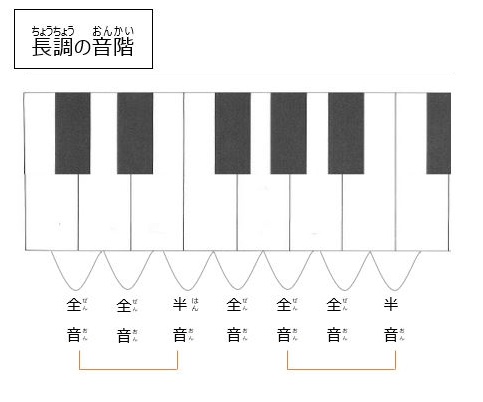
ハ長調の音階で、実際に音の幅を確認
音階は、上の図のように、
【全音・全音・半音】全音【全音・全音・半音】という音の幅で出来ています。
この音の仕組を覚えておけば、最初の音からすぐに音階が作れるというわけです。
呪文のように覚えると簡単!
この順番を覚えましょう。
大丈夫、簡単です。
【ぜ・ぜ・は・ぜ・ぜ・ぜ・は】と覚えればいいです。
呪文のように唱えましょう。

ぜ、ぜ、は、ぜ、ぜ、ぜ、は

ぜ、ぜ、は、ぜ、ぜ、ぜ、は
短調は長調とは違う“スタート地点”でできている
この音階は、長調の仕組みで、短調の仕組はまた変わってきます。
長調の“ラ”から始まる=自然短音階
短調は、長調の音階のラの音に当たる部分から始まります。
なので、全音・半音・全音・全音・半音・全音・全音となるんです。
仕組みが覚えられたら、この音の幅を使って、
全部の長調の音階を確認してみましょう。
まとめ|覚えるより“仕組み”が一生モノ!
・調の丸覚えは大変だ!という方、
・指で覚える時間が取れない方
は、仕組みで覚えましょう!
音階の仕組みは、弾いてみて初めて「なるほど!」と感じることも多いもの。
理論は実践とセットで身につきます。弾きながら確かめてみましょう。
関連の小さなヒントや活用アイデアは、メルマガでもお届けしています。
メルマガはこちらから↓