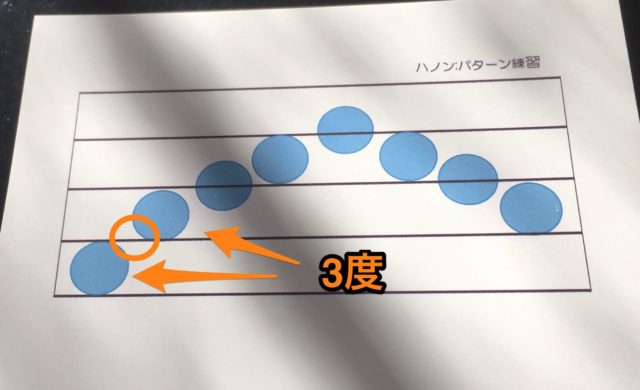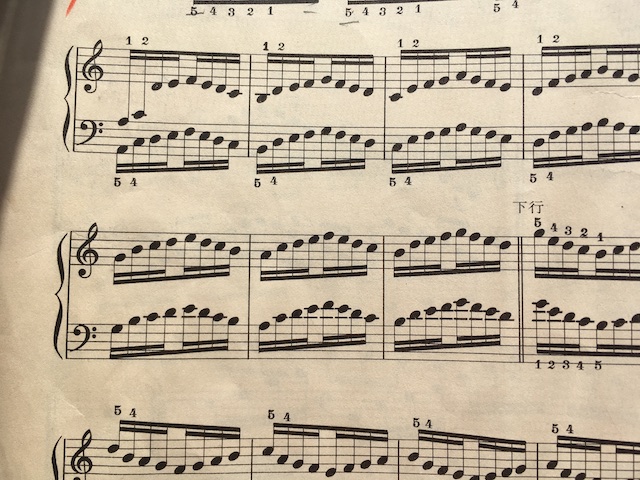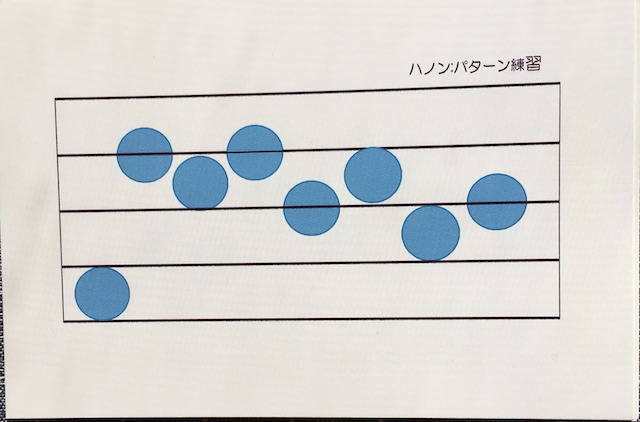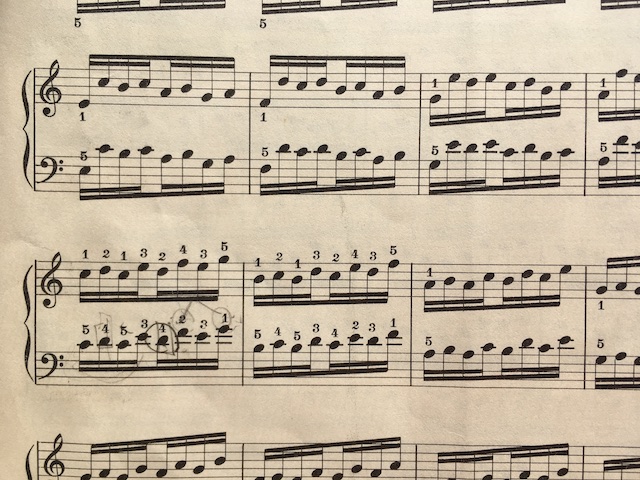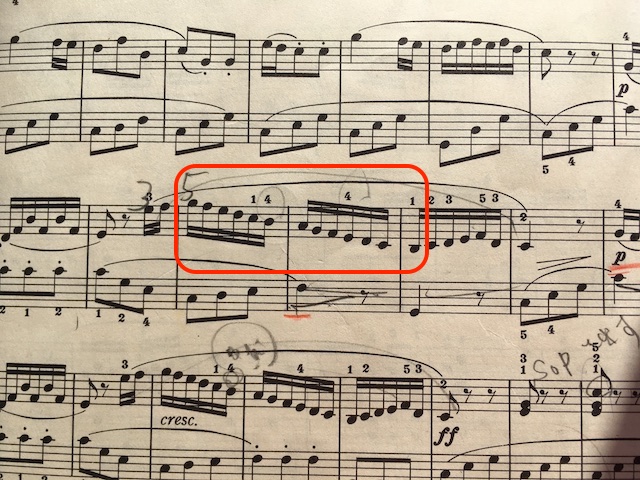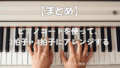こんにちは、いのうえちづよです。
譜読みには、「1音ずつ読む方法」と「音の流れを模様として捉える方法」の2種類があります。
後者の“パターン読み”を覚えると、スムーズに音楽を理解できるようになります。
今日はそのお話です。
音の上がり下がりを“パターン”として読む方法
譜読みには、音の上がり下がりを、パターンとして、音を読んでいくという方法があります。
この方法だと、実は、1つ1つの音を読むという手間がかかりません。
このパターン読み、どんな場合に使われるのかというと、
- 決まった音形をパターン化して読む
- 楽譜の中の音をパターンとして読む
という場合に使うと楽です。
一つ一つ、ご説明しますね。
ハノンに学ぶ「決まった形=パターン」を読む練習
ハノンの練習曲は、同じ指の動きを繰り返しながら上下に進むパターンの宝庫です。
たとえば、最初の2音の間が「3度」、他は「2度」で上昇するなど、音の動きを“模様”で捉えると譜読みが簡単になります。
これの代表的な本といえば、テクニック本ですね。
同じ指の動きを、繰り返しながら、音が、上がっていくものがあります。
一番わかり易い楽譜と言えば!ハノンですね。ご存知ですか?
ハノンって、決まった形で、上下に移動しています。
なので、これをパターン化して読むと譜読みがとっても楽です。
1番のパターンは、こういうものです。
1番最初の音と2番めの音の間には、音が1つ挟まっています。
こういう音の幅は、音楽でも【度】を使って、この場合は、3度といいます。
それ以外の音は、1つずつ移動しているので、2度です。
このパターンで、全体の音が1つずつ上がっているのがわかりますよね。
なので、1つずつ音を譜読みしなくても、パターン読みの方が、楽ですね。
次のパターン化はこの曲です
このパターンは、何番かお分かりでしょうか?
曲を弾いたことがなくても、最初の音を決めたら、パターン通りに指を動かしていくだけです。
この音形で、音がわかるんですね。
しっかりと音の順番も頭に入れましょう。
答え合わせは、5番ですね。
教室でも、ハノンを使う時には、パターンカードで、譜読みの説明をしています。
このハノンを使う時は、譜読みではなくて、指の動かし方を第一に学んで欲しいと思っているからです。
楽譜の中にもパターンはたくさんある!
童謡「かえるのうた」でも
ド・レ・ミ・ファ → ファ・ミ・レ・ド
というように、音の上がり下がりがくり返されています。
似た形を見つけたら「最初の音だけ確認して、あとは模様の通りに指を動かす」だけでOKです。
例えば、こういう音形ですね。
これは、音階のパターンです。
始まりが、ソの音。
終わりがシ。
ひたすら、1音ずつ下るだけです。
指遣いは、音階(=スケール)の勉強をしていたら、すぐに弾けるはず。
他にも、楽譜の中にパターンって本当にたくさんあります。
和音などもでてきますね。
ショパンのエチュードなど弾かれている方は、お気づきでしょう。
音階と和音のパターンの羅列ですね。
結局、音楽は、基本練習のまとまりで出来ているんです。
童謡などにも、よくでてきますよ。
例えば、童謡の『かえるのうた』。
最初の部分は、
『ド・レ・ミ・ファ・ミ・レ・ド』
という音の並びです。
まずは、ここでは、全部の音が、1つずつ4つ(4度)音があがって、
また同じように1つずつ今度は3つ(3度)下がって、元の音に戻っている・・と考えます。
これが、パターン化ということです。
他にも曲の中に、同じような音のパターンはないか、探します。
もう一つ同じような部分が見つかります。
『ミ・ファ・ソ・ラ・ソ・ファ・ミ』
この部分は、同じパターンというのが確認できたら、
最初の音だけが解れば、後は、パターンに沿って、指を動かすだけですね。
どうです…?
ちょっと譜読みが楽になりませんか?(*^-^*)
他にも、ショパンやベートーヴェンやモーツァルトの譜読みでも使える方法です。
大人の初心者さんにこそおすすめの読み方
パターン読みは、楽譜を“模様”として見られるようになるため、
いちいち音名を数えなくても、全体の流れを自然に理解できるようになります。
慣れると初見演奏にも役立ちますよ。
子どもの生徒さん達には、譜読みが出来るようになってから、教えています。
楽で、音を読まなくなってしまうんですよね〜^^;
まとめ|“音の模様”を見つける目を育てよう
1音ずつ読む方法に加えて、音の上がり下がりをパターンとして読む練習を取り入れてみましょう。
きっと譜読みがラクになり、音楽の流れを感じながら弾けるようになります。
楽しい、音楽活動にお役立てくださいね。
🎵譜読みが苦手…そんな時は、音を「数える」のではなく「模様で見る」練習を。
メルマガでは、初心者さんの譜読みをラクにする“視点のコツ”をやさしくお伝えしています。