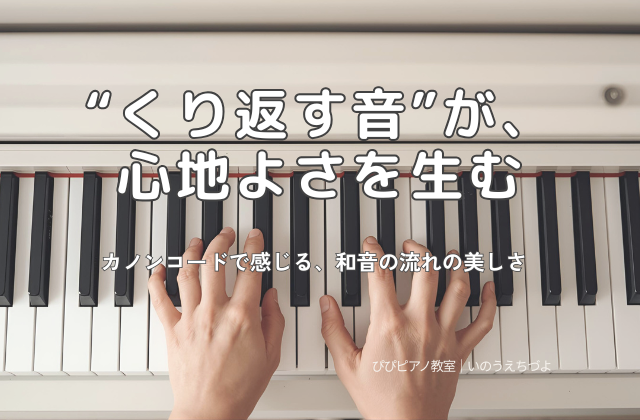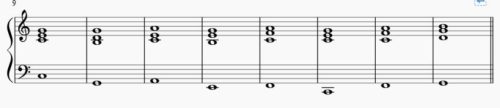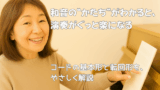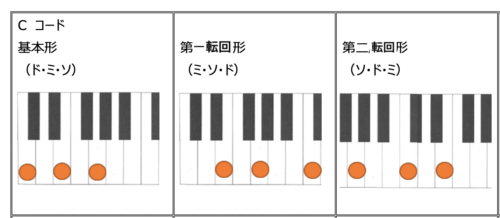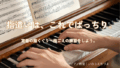こんにちは。いのうえちづよです。
今日は、カノンコードについて書いてみようと思います。
カノンコードとは?
「カノンコード」とは、“カノンの技法”をもとに作られた曲で使われる**和音の並び(コード進行)**のことです。
特に有名なのは、パッヘルベル作曲の《カノン》。
日本でも「スピッツのチェリー」「にじいろ(綾香)」「少年時代(井上陽水)」など、多くの名曲にこの進行が使われています。
カノンの技法とは
「カノン」とは、同じメロディを少しずつずらして重ねていく音楽の仕組みです。
いわば“輪唱”のようなもので、メロディやリズムを少し変化させながら追いかける形で進みます。
この技法が生み出す“心地よいくり返し”が、聴く人に安定感と深い感動を与えるのです。
カノンコードの並びを見てみよう
ハ長調(Cメジャー)のカノンコードは次の並びです。
C → G → Am → Em → F → C → F → G
この並びを順に演奏するだけで、パッヘルベルのカノンの伴奏ができます。
💡たとえば、Cコードは「ド・ミ・ソ」、Gコードは「ソ・シ・レ」。
並べて弾くと、自然な流れで音が進んでいくのが感じられます。
ハ長調で作られている曲の場合、カノンコードの最初の和音は、C(=ド・ミ・ソ)になります。
その調の最初の和音(=主和音)から始まっています。
次が、Ⅴ(5)の和音である、G=ソ・シ・レ
その次が、Ⅵ(6)の和音のAm=ラ・ド・ミ
次は、
Ⅲ(3)の和音の Em=ミ・ソ・シ
Ⅳ(4)の和音の F=ファ・ラ・ド
Ⅰ(1)の和音の C=ド・ミ・ソ
Ⅳ(4)の和音の F=ファ・ラ・ド
Ⅴ(5)の和音の G=ソ・シ・レ
最初に戻って
Ⅰ(1)の和音のC=ド・ミ・ソ
となって、カノン進行のコードの並びは、
となります。
音で表すとこんな感じです↓
この順番で演奏すれば、パッヘルベルの曲の伴奏が出来ます。
この順番が、カノン進行。
和音を両手で弾く場合の一つの方法として、「左手は根音、右手はその和音で使われている音」でしたね。
和音を両手で弾く時のアレンジについての記事はこちらから↓
よく音を見て頂ければ、おわかり頂けるように、左手は、いつものように根音だけで弾いているのですが、パッヘルベルのカノンのメロディになっています。

という事は・・・

ちゃんと、そのコードの中の音が使われて、メロディが出来ているということ・・?

演奏のコツ|転回形を使ってなめらかに
すべてのコードを基本形(ドミソのようにまっすぐ)で弾くと、手の移動が大きくなり弾きにくいですよね。
そんなときは転回形を使うと、近い位置の音でつなげられるのでスムーズに弾けます。
たとえば、
最初に「C=ドミソ」を弾いたら、次の「G=ソシレ」は“シ”が近いので、
「ド → シ」へ移動するように弾くと自然です。
転回形と呼ばれる和音の形に直すことをおすすめします。
画像の右側の2つですね。⬇️
転回形は、なるべく近くの音で和音を弾く場合と考えてください。
最初にドの音を弾いたら、次の和音はG(ソ・シ・レ)の中のシが近いですね。
ドからシに移動して演奏するという事になります。
まとめ
カノンコードは、
C・G・Am・Em・F・C・F・G
という並びで構成されています。
覚えてしまえば、どんな曲にも応用できる万能な進行です。
まずはゆっくりと弾いてみて、和音の“響きの変化”を感じてみてくださいね。
🎵「コードが難しそう…」と感じる方へ。
メルマガでは、和音の仕組みやアレンジの考え方を、やさしい例で少しずつお伝えしています。
あなたの“耳と手”がつながるように、ゆっくり練習していきましょう。