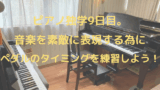こんにちは、 いのうえちづよです。
今日は、ピアノのペダルの使い方についてお話しします。
右側のダンパーペダルについてです。
ダンパーペダルの使い方
ピアノの右側にあるペダルで、「サスティンペダル」とも呼ばれます。
鍵盤を離しても音を響かせることができ、音に余韻を与える役割を持っています。
ペダルを踏むタイミングが大事
ダンパーペダルは「音を鳴らしてから踏む」のが基本です。
打鍵と同時に踏んでしまうと、せっかくの響きがぼやけてしまいます。
音を出してからペダルを踏むと、弦を押さえているダンパーが上がり、音が自然に残響します。
このタイミングを体で覚えると、演奏がぐっと滑らかになります⬇️

ペダルの仕組みを理解しておこう
ペダルを踏むと、ピアノの中で「ダンパー」と呼ばれるフェルトが弦から離れ、音が止まらずに響き続けるようになります。
これが“サスティン効果”です。
指を離しても音が鳴り続けるので、旋律に余韻をもたせることができます。
こちらの記事でペダルの仕組みについて詳しく説明しています↓
この仕組みを使って演奏すると、音楽が素晴らしく生き生きと表現できるようになります。
今まで、規程の長さだけ響いていた音が、ペダルを使う事で音に余韻を持たせてさらに響き渡らせる事ができるんです。
こんな時にダンパーペダルを使おう
- 音に余韻を残したいとき
- 弱いタッチを補いたいとき
- メロディをつなげたいとき
特に「音を保ちたいけれど指を離さなければならない」ような場面では、ペダルが大活躍します。
まとめ|ペダルで音楽に“息”を吹き込もう
音を鳴らしたあとにペダルを踏むことで、音の流れがなめらかになり、演奏に深みが生まれます。
無理に多用せず、フレーズのつながりを意識して使ってみてください。
きっと音楽の表情がぐっと豊かになりますよ。
ペダルの響き方ひとつで、演奏の印象は大きく変わります。
メルマガでは、初心者さんが「耳で響きを感じる練習」を身につけるヒントも配信中です♪